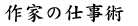森村誠一
聞き手:角川ミステリ編集部
作家であり続けること
―― 作家になることよりも、作家であり続ける方がよほど難しく、また、元政治家や元大学教授はいても、元作家と言うのはありえないので、作家たる者、生涯作家であり続けなければならないという、お話をされているのを何度か伺ったことがあります。そのお話を伺うたびに、作家であることの凄みを感じるのですが、その緊張感を持ち続けておられる、根の部分には、なにが潜んでいるのでしょうか。
作家は、前作家、元作家とは言われないように、書くことをやめた瞬間から、本質的には作家ではなくなります。書くことを止めた作家が作家と呼ばれていても、それは作家の”余韻”です。作家は職業ではなく、状態であるという説も、その辺の事情を裏書しているのでしょう。
作家にはほかの職業にはないうま味もあります。そのうま味には中毒性があります。一定期間書きつづけて、その収入によって生計を立てるのですから、一応職業と呼んでよいでしょう。ただの一作によって大ベストセラーを出せば、1年ないし数年は遊んで暮らせます。若くしてスポットライトを浴びて、一躍全国的に有名になる人もいます。翻訳されれば、その名前は海外にまで知られます。それほどではないにしても、自分の作品世界が活字になって、広く読者に紹介されることは、一度でも自分の本を出した経験のある人には、忘れられない感激と喜びでしょう。そのために、一生、文学中毒に取り憑かれる人もいます。
職業作家は作家である限り、書きつづけなければならないという宿命を負わされています。日本語を知っている者であれば、誰でも一、二作は自分の人生という小説を書くことができます。しかし、書きつづけるという作業は並大抵ではありません。それができるのは、気力と体力と、熟練や慣れがあるからです。
職業作家としてある程度の実績ができると、加速度がつきます。この加速度によって作品を書きつづけられます。会社で働く人間は、どんなによい仕事をしても、会社の枠に閉じ込められています。自分の食材ではなく、会社という他人からあたえられた食材で料理を作っている料理人のようなものです。作家は自分の食材で料理(作品)を作ります。作品を書くために、最もよい環境をつくり、ライフスタイルを送れます。劣悪な労働環境や、不愉快な人間関係に耐えて働かなければならない組織人間とは大きくちがうところでしょう。この辺が作家のうま味です。
しかし、そこに文芸の毒が仕掛けられています。作家は実績や名前に驕(おご)って、楽をして仕事をしやすい環境にあります。虚名に走って本分を忘れることがあります。その間に作品がどんどん劣化していきます。劣化しても、読者の受けがよい場合もあるので、作家自身がスポイルされていきます。それが自家中毒性の強い文学中毒の怖いところです。読者の支持は無責任で、信用できません。時代に耐えた古典ですら虚名があります。作品を裁く者は、結局、作家自身であり、楽をしたり、読者を欺瞞(だま)したりした作品は、一生、いや、死後までもその作者の負債となってついて回ります。文芸のうま味とは怖さと言えましょう。
―― 示唆深いお話をありがとうございます。これまでも、なんども質問されたことかとは思うのですが、ホテルマンから作家になられるとき、小説を書こうとしたきっかけはどんなものだったのでしょうか。
最終学校を卒業して、最初の就職先のホテルに約十年いる間に、自分は労働力の一単位にすぎないということをいやというほどおもい知らされました。自分が会社(ホテル)を辞めても、すぐに代替(かわり)が見つかり、十年の足跡がホテルのどこにも残っていない、いてもいなくても同じような存在であることが虚(むな)しくなりました。たとえどんな小さなニーズであっても、私以外にはできないような仕事をしたいとおもい立ち、もともと本が好きであった私は、文芸の分野に路線変更したのです。ホテルマン時代、私のいたホテルに梶山季之氏や笹沢左保氏など、多数の作家が来館したことも大いに刺激になりました。
ホテルマンの時代は、毎日出勤するとき、少しずつ自殺をしているような気分でしたが、いまおもえば所を得なかったホテルマン時代に、私は作家としての基礎である絶好の人間観察の舞台と機会をあたえられたのです。いまでも私はホテルを、私の人生の母社とおもっています。
ホテルマン時代、私は下宿を探すとき、近所に貸本屋と風呂屋のあるところを必須条件としていました。当時、貸本屋で耽読したのが松本清張、高木彬光、笹沢左保、山田風太郎、佐野洋、鮎川哲也の各氏、また早川ポケットミステリーの海外諸作品でした。貸本屋が閉店するとき、その店にあったHPB(早川ポケットミステリー)を一冊十円(当時平均二百五十円くらい)で全部買いました。そのHPB約百冊はいまでも私の書棚にあります。
作家の素地
―― その読書への耽溺は、おそらく、少年時代の読書遍歴から培われてきたものだと思うのですが、とくに傾倒していた、作家や小説はどんなものだったのでしょう。
生家は当時は珍しかった個人タクシーを経営して、オールズモービル、ビュイック・シボレーなど、アメリカ車を数台所有して、生活は豊かでした。私は町で有数の読書少年で、父は私が欲しがる本をなんでも買ってくれました。『少年倶楽部』と山中峰太郎、江戸川乱歩、大下字陀児、高垣眸、また漫画の『のらくろ』や『冒険ダン吉』などは最強のカードで、これらを持っていると、どんな本とでも交換して借りられました。戦前、戦中、町に貸本屋はなく、図書館はエンターテイメント系や漫画は置いていませんでした。『少年倶楽部』昭和8年7月号が欠けていて、それを町一番の肉屋の一年上級生が持っていると聞きつけた私は、彼に借りに行きました。だが、彼はもったいぶって貸してくれません。私は7月号が読みたい一心に、一年、その少年の家来となり、結局、彼が嘘をついていたことを知り、ただ働きさせられたことを今でも悔しくおもいだします。
戦後、町の商業高校へ入学した私は、二年生の第二学期、開業医であった叔父に頼んで偽の診断書を書いてもらい、一ヶ月、長期休学して、家には毎日、登校しているように見せかけ、町の図書館へ通い、『世界文学全集』の読破を試みました。一ヵ月後、さしも鷹揚な学校も不審を抱いて親に問い合わせ、『世界文学全集』はロシア、ドイツ、フランスを終わりイギリス、のオスカー・ワイルド作『ドリアン・グレイの肖像』で壮途(そうと)虚しく挫折しました。
特に愛読していたのは、ロマン・ロラン、ヘルマン・ヘッセ、ドストエフスキー、リルケ、日本では『平家物語』や『太平記』などの古典軍記、堀辰雄、立原道造、井上靖、吉川英治などでした。文体では井上靖、堀辰雄、ロマン・ロラン(豊島芳志雄訳)、詩歌では、立原道造、石川啄木に最も強く影響を受けました。
―― 作家になられて次々と作品を発表しながらも、新しいことに挑戦しつつ腕を磨いて行くにあたって、心がけておられたことはありますか?
作家になってから、読書の性格が変わってきました。一種のリサーチとして、名作・古典の読み直し、同業作家の先行作品、競合作品、受賞作品、問題作等を、時間のある限り読みます。これは自分の作品の栄養となり、作品を書きつづける刺激となります。ただし、最近は資料を読むだけで目が疲労し、読書量が絶対的に不足してきたのが不安です。
作家が本を読まなくなるということは、新しい才能にも触れられず、精神の他流試合の機会も少なくなり、作家として精神的鎖国状態になるので、極めて危険だと思います。また小説だけではなく、その他演劇、美術、映画、音楽等にもできるだけ接するようにしています。
―― 執筆にあたっての、ジンクスのようなものはおありなのでしょうか?書く前に必ずすることとか。
特にジンクスはありませんが、私は執筆日数を三日一単位(ワン・ユニット)と心得ています。長い間(今年で三十九年)書きつづけていると、仕事場に入るのがとても億劫なことがあります。そのようなとき、逃げてしまうと、竈(かまど)の火が消えてなかなかエンジンがかからなくなります。たとえ一枚でも二枚でも、毎日書くように心がけています。また一日、怠惰に過ごしてしまうと、二日目はもっと億劫になります。三日目はさらにいやになります。そして四日目、ここでようやくふたたび動き出すか、あるいは怠けつづけるか、ここが一般人とホームレスの境界線になります。四日目を怠けるとホームレス街道まっしぐら。ほとんどの人はここで立ち直ります。
作家の場合、個人差は大きく、怠け癖がつくと、一作だけで怠けの泥沼に沈んでしまうこともあります。このようなとき、私にとってなによりの刺激は、同業作家の凄い作品や、新人の才能です。おれも頑張らなければいけないとおもい直して、愛用のガラスペンを手にふたたびデスクに向かいます。ちなみに私のペンは特注のガラスペンで、総体二グラム。いまは生産中止で、二万本特注し、年間消費量約六百本、すでに一万二千本を消費して、残りの八千本は銀行の貸し金庫に保管しています。
―― 森村さんの作品には、様々な意味での社会と人間の関係を見据える視点がいつもあるように思うのですが、森村さんにとって、ミステリとはどういうものなのでしょう。
ミステリは言うまでもなく犯罪を扱っています。善行を扱っても一向にかまわないはずですが、例えば匿名の十億円の寄付者を探すとして、寄付者が探しだされたとしても表彰されこそすれ処罰されません。これが犯罪の犯人が捕まれば処罰されるので、犯人は必死に逃亡工作をします。ここに探偵と犯人の必死の攻防が繰り広げられ、興趣豊かな作品世界が築けるわけです。文学の永遠のテーマである人間と人生を描くにあたって、ミステリは犯人はだれか、一見不可能な犯罪をどのようにして実行したか、なぜそのような犯罪を犯したかなどを追求し、社会的動機である人間が最も描きやすい文芸形態だとおもっています。
マスコミとインターネットの発展によって、どんな山間僻地や絶海の孤島も、いまや社会的にリンクされていて、ソーローの『森の生活』のように、隠者といえども社会からの完全な隔絶は不可能な時代になっています。連絡不能の閉塞状況はミステリを構成する一つの重大な要素でしたが、携帯電話の普及したいま、ミステリにも新たな工夫が求められます。つまり、すべての作家は物質文明社会の影響下でミステリを構成しなければならない時代になったと言えましょう。一見、社会の影響をまったく受けていないような作家であっても、社会の構造の中に組み込まれています。
推理小説は民主主義の保証された社会に発展すると言われます。なぜなら、独裁社会や封建社会では犯人の人権は守られず、容疑者を捕らえて拷問にかけて自供させれば、一件落着です。論理的に犯人を創り出す必要はありません。容疑者と犯人の人権も守られてこそ成立する推理小説が、民主主義社会の指標となるいわれです。
―― これから、作家を目指している人に向けて、森村流指南をお願いします。
どのような動機から作家になるのも自由ですが、職業作家のほとんどは、自分の内に、これを書かなければ生まれてきた意味がない、これを発表しなければ生きている価値がないというふうにおもいつめて作家になった人たちです。収入や名声はその結果の副産物で、まず初めに作品ありきです。それ以外のものはその結果です。初めから結果だけを狙って書いても一向にかまいませんが、作家になろうとおもっても、すぐになれるものではありません。また、仮に作家になったとしても、いつまで書きつづけられるか保証はありません。一作一作にかける勝負師であり、書けなくなったときは存在価値のまったくない、粗大ゴミにすぎない者であるとの覚悟は必要です。
作家の条件
作家にとって必要な条件は、
一、 創造力(ものを創り出す力、想像力を含む)
二、 表現力
三、 構成力(作品世界をつくる力)
四、 取材力(純文学にはあまり必要ない)
五、 感性(感覚、嗅覚、視野、洞察力、分析力、など)
と言われていますが、これに持久力が必要となります。ただし、一作作家の場合は持久力は必要でありません。一作でも不朽の名作を残す確率があります。
角川ミステリ2002年7月号より